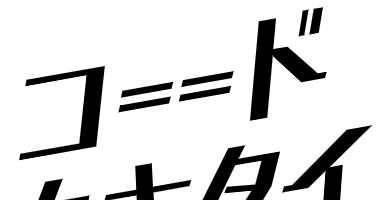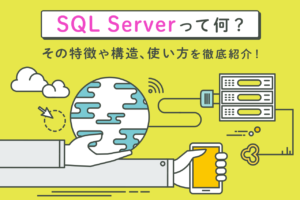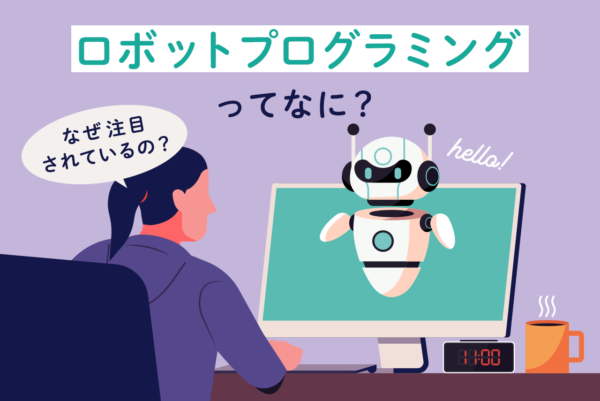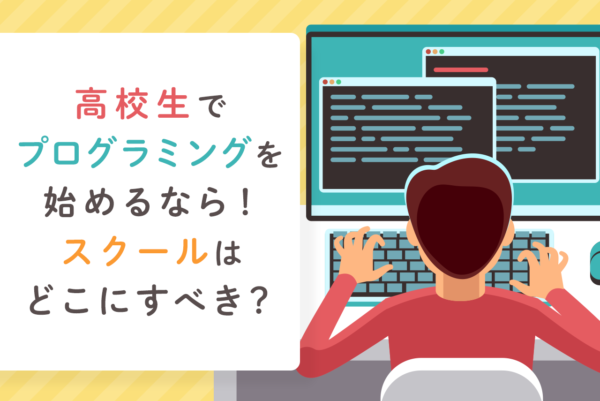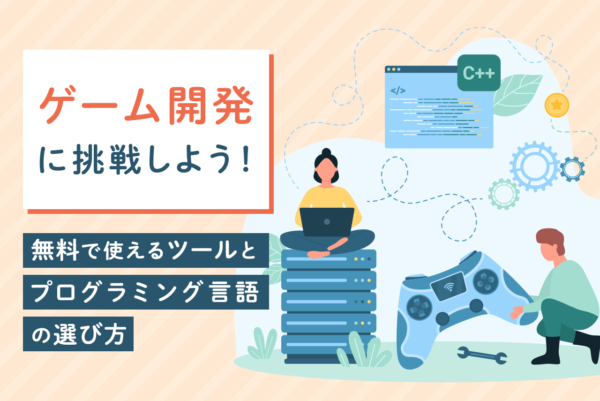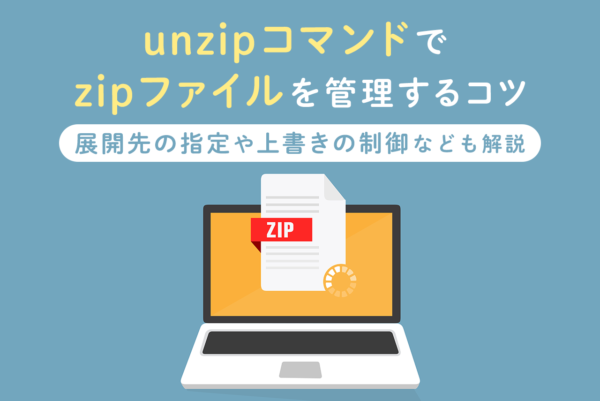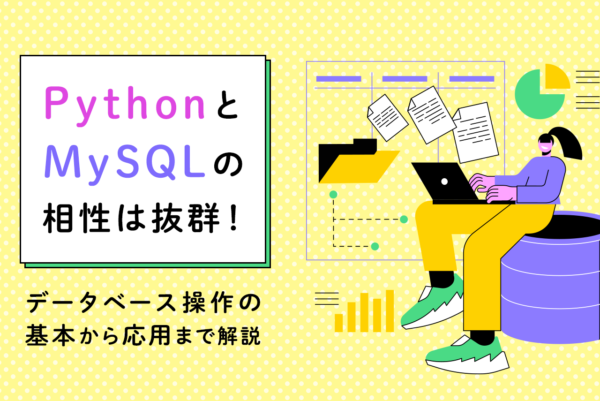本記事では小学校でのプログラミング教育の必修化に伴い、保護者の方に向けてプログラミング教育の目的と学習によって得られるものを解説します。あわせて、おすすめのプログラミング言語や学習教材なども詳しく紹介します。
小学校でのプログラミング教育が、2020年度より必修化されました。保護者の皆さんの中には、「どんなことを勉強するのかわからない」「早めに準備するべきか知りたい」という方もいるのではないでしょうか。
本記事では、小学校におけるプログラミング教育の目的と学習によって得られるものや、小学生のプログラミング学習に適している教材を解説します。おすすめのプログラミング言語や学習サイトについてもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
小学生のプログラミング教育の現状

プログラミングと聞くと、「難しい」というイメージを持つ方もいるかもしれません。プログラミング学習を経験したことのない保護者の方であれば、なおさら「小学生にプログラミングが理解できるの?」と疑問に感じるのではないでしょうか。
しかし、小学校で習うプログラミングは複雑なプログラミング言語の習得を目指しているのではなく、「プログラミング的思考を身につけること」を目的に掲げているのです。プログラミング的思考とは、物事を論理的に捉えたうえで、問題を解決するための過程を順序立てて考え、実行していくことができる「論理的思考力」のことを指します。
プログラミング教育は教科扱いされているわけではない
小学校でプログラミング教育が必修化されたものの、「プログラミング」が教科となったわけではありません。これまでの教科(国語・算数・理科・社会など)の授業内で、プログラミングを学習するのです。どの教科にプログラミングを取り入れるかは地域や学校によって異なりますが、算数や理科の授業でプログラミングを教えるケースが多く見られます。
いまある教科の授業内でプログラミングに親しんだり、プログラミング的思考を身につけたりするといった学習が、小学校のプログラミング教育です。そのため、専門的なプログラミングの授業がスタートするのは中学生以降となっています。
プログラミング教育は必須であるが具体的な学習学年は指定されていない
プログラミングは教科としては扱われていないことに加えて、具体的に何年生でどのようなプログラミング学習をするのかといったことも、学習指導要領の中で決められているわけではありません。学習内容の詳細については、各自治体の教育委員会や学校の裁量に任せられているのです。
文部科学省が公表する「小学校プログラミング教育の手引き」などでは、さまざまな学習事例が紹介されています。これらの事例から、プログラミングを活用する科目も各学年での学習内容も地域や学校によって異なることがわかります。
パソコンを使わずに学ぶことがある
多くの小学校では、子どもたちにパソコンやタブレットなどのICT機器に慣れ親しんでもらう狙いから、ICT機器を用いたプログラミング授業をおこなっています。
しかし、すべてのプログラミング授業でICT機器を使用するわけではありません。紙のカードやブロックなど、ゲームを通してプログラミングの基礎的な概念を習得する場合もあります。ICT機器を使わない学習方法を「アンプラグド・プログラミング」と呼び、低学年の子どもたちに向けて抵抗感なく楽しくプログラミングを学べる方法として利用されているのです。
小学生のプログラミング教育で得られるもの

小学校のプログラミング教育について、「早すぎるのでは」と戸惑う保護者の方もいるでしょう。しかし、実際には小学生からプログラミングを学習することで、将来につながるさまざまなメリットが得られます。
ここでは、主な3つのメリットを解説します。
- IT化していく社会で必要な知識が身につく
- 将来の選択の幅が増える
- 目的達成に必要な手段を理解して実行する能力につながる
IT化していく社会で必要な知識が身につく
IT化が加速する現代社会では、プログラミングはあらゆる業界で活用されています。プログラミングは限られた専門職の人だけが学ぶものではなく、今後の社会を生き抜くために誰もが身につけておきたい基本的な教養の1つとなっているのです。IT技術は日進月歩で進んでいます。プログラミングが必修化した世代の子どもたちが社会に出るころには、プログラミングの知識を仕事に活用することがごく当たり前になり、プログラミングの必要性はますます高まっていくと考えられます。
また、早いうちからスマートフォンやタブレットなどのICT機器の操作に親しむことで、タイピングをはじめとしたパソコンの初歩的なスキルの習得につながり、将来の役立つことは間違いないでしょう。
将来の選択の幅が増える
プログラミングを小学生のうちから学習すれば、将来の選択肢が増えます。
現代では自動車や交通システム・オンライン決済システム・スマートフォンアプリなど、日常生活のあらゆる場面でプログラミングが活用されています。プログラミングを活用したIT技術のニーズは、今後さらに拡大すると考えられているのです。
しかし日本ではいま、IT人材が足りないことが問題となっています。今後もIT人材不足は懸念されており、IT人材がより必要とされる時代が到来することでしょう。
また、IT業界以外でもプログラミングを活用したサービス開発や業務効率化が日常的におこなわれているため、将来どのような業界で働くにしても、プログラミングは有効なスキルとなるのです。
目的達成に必要な手段を理解して実行する能力につながる
プログラミングを学習することで、目的達成に必要な手段を理解して実行する力が育めます。
コンピュータを思い通りに動作させるためには、明確な指示を与える必要があり、この指示が「プログラム」です。どのような指示を出せば自分が意図するようにコンピュータが動作するのかを考える機会を増やすことで、創造力や想像力も習得できるでしょう。
物事を順序立てて考える力や創造力を養うのは簡単なことではありませんが、プログラミング学習を通して、楽しみながら自然にこのような力を育めるのです。
小学生がプログラミング教育で学ぶ言語とは?
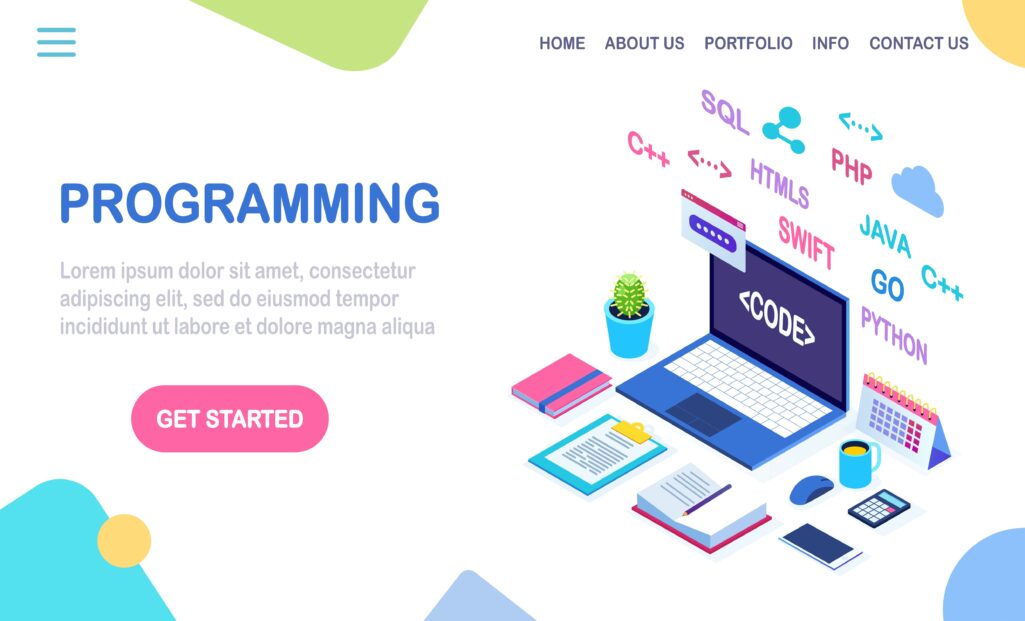
ここからは、実際に小学生がプログラミング教育で学ぶ言語について紹介します。
プログラミング言語は、大きく2種類に分けられます。1つは文字や記号・数字のみで記述する「テキストプログラミング言語」で、「Python」「JavaScript」「PHP」などがその代表例です。プログラミング言語と聞くと、このテキストプログラミング言語をイメージする方が多いでしょう。
もう1つは、小学生が学ぶ「ビジュアルプログラミング言語」で、Scratch(スクラッチ)が代表例です。ビジュアルプログラミング言語は、テキストプログラミング言語を易しくした言語で、カードやブロックを配置してプログラミングをしていくものです。
小学生のプログラミング教育におすすめのプログラミング言語
次の2つは代表的なビジュアルプログラミング言語で、小学校のプログラミング教育におすすめです。
- Scratch(スクラッチ)
- Viscuit(ビスケット)
それぞれ詳しく解説していきます。
Scratch(スクラッチ)
Scratch(スクラッチ)は全世界150国以上で使われているプログラミング言語で、小学校のプログラミング教育の定番ともいえる言語です。指示が書かれたアイコンをドラッグ&ドロップで操作し、プログラムを組み立てることにより直感的な操作で自作のゲームやアニメーション作品が作れます。このように、小学生でも楽しみながら学習に取り組みやすくなっている点が特徴です。
Scratch(スクラッチ)のソフトウェアは無料で使用でき、Web上で操作できるため、パソコンとインターネット環境さえあれば手軽に学習を始められます。またオンラインコミュニティでは、自分の作品を公開したり他のユーザーの作品を参考にしたりできる仕組みがあるため、スキルアップや疑問の解決に活用できます。
Viscuit(ビスケット)
Viscuit(ビスケット)も、Scratch同様に小学校のプログラミング教育で使われているビジュアルプログラミング言語です。コードの入力ではなく「メガネ」と呼ばれるツールを使うことで、絵本やアニメーションを作成できます。自分が描いた絵を動かせるので、子どもは遊びの延長で楽しくプログラミング学習に取り組めるでしょう。
パソコンのブラウザ上で利用できるほか、スマートフォンやタブレット向けのアプリでも利用できます。Viscuitは日本製であることから、公式サイトも日本語で表記されており、使い方が理解しやすい点もおすすめポイントの1つです。
小学生のプログラミング教育におすすめの6つの教材

ここからは、小学生のプログラミング教育におすすめする6つの教材を紹介します。
- microbit(マイクロビット)
- QUREO(キュレオ)
- レゴ ブースト
- マインクラフト
- レゴ SPIKE プライム
- ニンテンドーラボ
microbit(マイクロビット)
microbit(マイクロビット)は、LEDやスピーカー・加速度センサー・磁気センサー・温度センサーなどを搭載したマイコンボードです。プログラミングによってコントロールが可能な学習教材です。microbitが開発されたイギリスでは、11歳~12際の子どもに無償で配布され教育現場で広く活用されています。
プログラミングによってmicrobitのLEDを光らせたり、文字や図形を表示させたりといったさまざまな操作が可能です。microbitを使うためには、microbit本体とパソコンとを接続するケーブルや電池などを買いそろえる必要があります。
QUREO(キュレオ)
QUREO(キュレオ)は、Scratchをベースに開発された子ども向けプログラミング教材で、全国2,000以上の学習塾や教育現場での導入実績があります。本物さながらのゲーム作りを通して、楽しく学習に取り組める教材です。
Scratchと異なる点は、プログラミングの基礎を順序立てて学習できるカリキュラムが準備されていることでしょう。QUREOは2024年度から開始する大学入試も見据えて設計されており、「プログラミング能力検定」のレベル1〜4に対応する学習内容となっているのです。
レゴ ブースト
レゴブーストは、レゴブロックと組み合わせて使用可能なプログラミング学習キットです。シンプルなプログラミングを通じて、自分の組み立てたレゴを思い通りに動かして遊べます。
適齢の子どもであれば、専用アプリの詳細な指示に従いながら大人の助けを借りずともブロックの組み合わせ方やプログラミングの方法を習得できます。また、ステージをクリアすると次のステージに進めるため、ゲーム感覚で楽しく遊べる点も魅力です。
多くの子どもにとってなじみ深いレゴブロックを用いるため、抵抗感なくプログラミング学習を始められるでしょう。
マインクラフト
マインクラフトは、世界中の幅広い世代に親しまれているゲームです。
マインクラフトはゲームの世界がサイコロ状のブロックで作られており、ブロックを使って建物を作ったり探検したりして遊べます。ゲームを進めながら楽しくプログラミングを学習でき、創造性が刺激される教材である点もおすすめの理由です。
マインクラフトには、Java版と統合版の2種類があります。両者のゲーム内容には違いがないものの、扱えるパソコンやゲーム機が異なるため購入の際には注意が必要しておきましょう。
レゴ SPIKE プライム
レゴ SPIKETM プライムは、小学校高学年から高校生までが対象で2020年1月にリリースされた製品です。学習カリキュラムとScrachがベースのビジュアルプログラミング言語・ロボットキットが一体となっており、ものづくりを楽しみながらプログラミングを学習できます。タブレットを活用してドラッグ&ドロップでおこなうプログラミングのため理解がしやすいです。
ただし、レゴ SPIKETM プライムは小学校高学年を対象にしているだけに、他の教材と比較してやや難易度が高いため、プログラミングの基礎を学んでから使用することをおすすめします。
ニンテンドーラボ
ニンテンドーラボは、ダンボール製のパーツを組み立てて作成した専用コントローラを用いてゲームを楽しめるニンテンドースイッチのゲームソフトです。必要なパーツはすべて同梱されており、スイッチ上で見られる丁寧な解説で作業の進め方が理解できます。そのため、子どもでも容易に作成できます。付属のキットのみなら、オリジナルの工作を使ってのプログラミングもできるため、自然と創造力が身につくでしょう。
とくに”ラボ Toy-Con ガレージ”では、ビジュアルプログラミング風の機能を利用できます。そのため、Scratchなどのビジュアルプログラミング経験がある子どもは、スムーズに進められるでしょう。ただし、ニンテンドーラボ全体の使用にScratchの経験が必要なわけではない点に注意が必要です。
小学生のプログラミング学習に3つのおすすめの学習サイト

小学生向けのプログラミング学習サイトは、いくつもあります。それぞれのサイトによって学習目的や特徴が異なるため、どのサイトで学習したらよいのか迷ってしまう方もいるでしょう。ここでは、とくにおすすめの学習サイトを3つ紹介します。
WONDER!SCHOOL

引用:プログラミング部 | 部活トップ | バンダイによる、遊びと学びのココロ育むファミリーエンタメサイト
WONDER!SCHOOLは、株式会社バンダイが運営する小学生向けの無料学習サイトです。さまざまな「部活動」をテーマにしたコンテンツが用意されており、その1つにプログラミング部があります。プログラミング部では、ドラえもんをはじめとした人気キャラクターのゲームで楽しみながら、プログラミング的思考を鍛えることが可能です。プログラミングの授業動画や誰でも作品を投稿できるコーナーなども用意されています。
KOOV

ソニーが運営する、子ども向けのオンラインプログラミング学習サービスが「CREATE by KOOV」です。月2回のペースで配信されるコンテンツに従って、ロボット・プログラミング学習キット「KOOV」を使ってブロック・プログラミング・工作に取り組みます。
CREATE by KOOVは教材費と月額受講料がかかりますが、ロボット・プログラミングを学習できるオンライン講座の中でも低価格であるため、手軽に始めやすい点が魅力です。
Code Studio
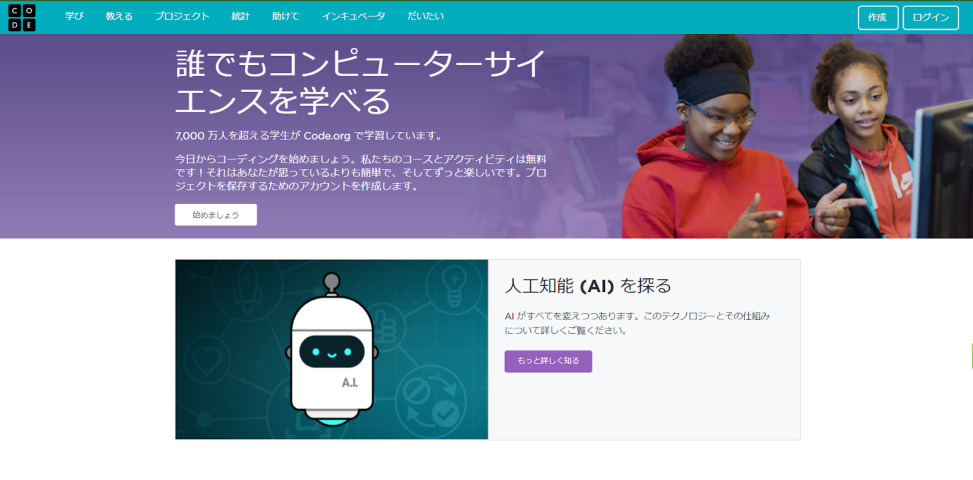
引用:Learn Computer Science – Code.org
Code Studioは4歳からを対象としたプログラミング環境で、アメリカで普及しつつあるサービスです。ビジュアルプログラミング言語がメインですが、「JavaScript」でのコード入力にも対応しています。そのため、プログラミングの基礎を習得したら、「JavaScript」の学習へとステップアップも可能です。ほかにもマインクラフトやアナと雪の女王などの人気作とコラボレーションするなど、カリキュラムには幅広い年齢が楽しめる工夫が凝らされています。
小学生のプログラミング教育におすすめの教室を解説

「自宅学習に自信がなく、いつでも質問できる環境がほしい」という方であれば、プログラミング教室を検討するのもよいでしょう。ここからは、小学生のプログラミング教育におすすめする次の2つの教室を紹介します。
- N Code Labo
- リタリコワンダーオンライン
N Code Labo

引用:小学生・中学生・高校生のプログラミング教室【N Code Labo】│角川ドワンゴ学園運営
N Code Laboは学校法人角川ドワンゴ学園が運営しているプログラミング教室です。通学コースとネットコースとがあり、通学コースは東京都・神奈川県・大阪府の合計4カ所の教室で少人数指導が受けられます。ネットコースでは、オンライン授業によるプロ講師の個別指導の受講が可能です。
独自のカリキュラムには、角川ドワンゴ学園が運営するN高等学校でのプログラミング教育のノウハウが活かされています。小さな子どもでも実践的なプログラミングが学べるため、多くの保護者に支持されています。無料体験授業が全教室で開催されているため、気になる方はぜひ参加してみてください。
リタリコワンダーオンライン

引用:年長・小学生からのロボットの教室ならLITALICO(りたりこ)ワンダー|LITALICO
リタリコワンダーオンラインは、幼稚園の年長児から高校生までを対象としたプログラミング教室です。通学かオンラインの授業スタイルを選択でき、通学する場合の教室は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にあります。オンライン授業は生徒2人以内の少人数制のため、学習を主体的に取り組みやすいといった特徴があります。
ゲーム制作やWebページ制作・ロボット製作などのコースが全部で5種類あり、子どもの興味に応じたコースを選べる点も魅力です。無料体験は公式サイトから手軽に申し込むことができます。
小学生のプログラミング教育におすすめの教室を解説!

小学校のプログラミング教育の目的や、おすすめの学習方法を解説しました。小学校のプログラミング教育必修化に伴い、子どもたちが興味を持ってプログラミングを学べる教材やサービスが多く登場しています。プログラミング学習によって身につく力は、将来を見据えたうえでも非常に有益です。本記事を参考に無料で手軽に試せるものから、親子でプログラミングの面白さに触れてみてはいかがでしょうか。
アクセスランキング 人気のある記事をピックアップ!
コードカキタイがオススメする記事!

2024.06.17
子供におすすめのプログラミングスクール10選!学習メリットや教室選びのコツも紹介
#プログラミングスクール
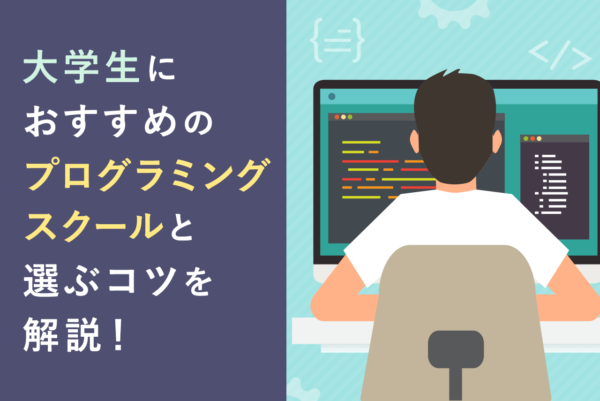
2022.01.06
【完全版】大学生におすすめのプログラミングスクール13選!選ぶコツも詳しく解説
#プログラミングスクール

2024.01.26
【未経験でも転職可】30代におすすめプログラミングスクール8選!
#プログラミングスクール

2024.01.26
初心者必見!独学のJava学習方法とおすすめ本、アプリを詳しく解説
#JAVA

2024.01.26
忙しい社会人におすすめプログラミングスクール15選!失敗しない選び方も詳しく解説
#プログラミングスクール

2022.01.06
【無料あり】大阪のおすすめプログラミングスクール14選!スクール選びのコツも紹介
#プログラミングスクール

2024.01.26
【目的別】東京のおすすめプログラミングスクール20選!スクール選びのコツも徹底解説
#プログラミングスクール

2024.01.26
【無料あり】福岡のおすすめプログラミングスクール13選!選び方も詳しく解説
#プログラミングスクール

2024.01.26
【徹底比較】名古屋のおすすめプログラミングスクール13選!選び方も詳しく解説
#プログラミングスクール

2024.01.26
【徹底比較】おすすめのプログラミングスクール18選!失敗しない選び方も徹底解説
#プログラミングスクール